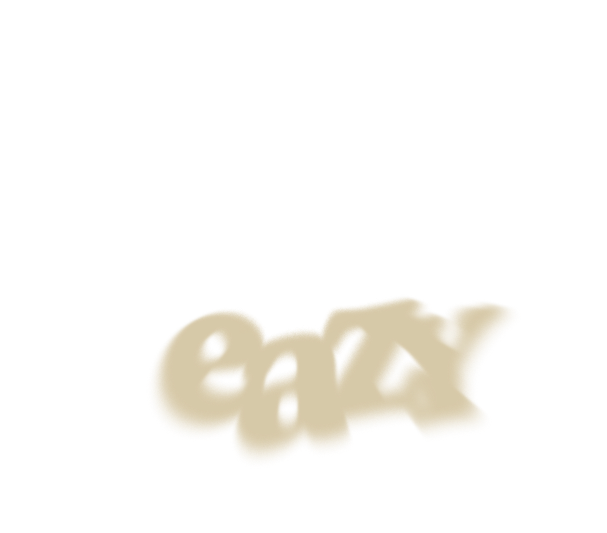アクションカメラは魔法の道具ではありません。
広告やマーケティングを鵜呑みにしないでください。
選び方を間違えると必ず後悔します。
このページでは過去にカメラ選びをミスってきた僕がどんなミスが起こりうるのか、どうやれば避けられるのかについて語っていきます。
この記事の対象者
- アクションカメラを検討中
- メーカーや機種の違いがまだよくわかってない
- 失敗せずに選びたい
この記事でわかること
- アクションカメラ選びの落とし穴
- カメラ選びの考え方
実績

YouTubeチャンネル「Action Camera Days」運営
実際の撮影風景・使い方を配信中
登録者1200人以上
動画50本以上
アクションカメラユーザーのリアル
ここからは長期間のアクションカメラユーザーとして学んできたことをお伝えしていきます。
1. 巷のアクションカメラ情報はすべてが真実とは限らない
アクションカメラの情報を日々チェックしていると、ネット上には予想や噂、レビューなど多くの情報が溢れています。
中には「次回作の予想」や「評価の高いレビュー」もありますが、かなりの確率で外れていたり、偏った情報であることも少なくありません。
僕自身、YouTubeでの紹介をきっかけにカメラを購入した経験が何度もあります。
しかし後になって、「なんだ提供案件だったのか」と気づくこともあります。
情報発信者の中には、メーカーから提供を受けてレビューしている人も多くいます。
僕自身、提供を受けるのでわかるのですが、案件だとたとえ発信者が誠実でも、メーカー側の意向に沿った内容になりやすいです。
たとえば:
資料を元に構成されたレビュー動画(そのまま言ってるな…という内容)
建前としての褒め言葉が並び、本音が見えにくい紹介
もちろん、中には本当に良いと思って紹介している人もいますし、案件でも有益な情報はあります。
でも、「中立な意見だ」と思い込んで受け取るのは危険です。
アクションカメラ選びでは、情報の出どころや背景を冷静に見極めることが大切です。
2. どんどん膨らむ追加費用本体価格に騙されるな
本体だけだと買いやすく見えますが、実際はアクセサリー(バッテリー・マウントなど)で倍額になることも珍しくはありません。
本体を買うと「もうここまで来たし…」と自分を説得して投資してしまうんですね。
断言します。一部の必須アクセサリーを除いて、即買いしないでください。90%以上は使わなくなります。
3. アクションカメラユーザーのリアル失敗談と学び
故障時の手続きは想像以上に面倒
主要なアクションカメラメーカーの多くは海外企業です。
そのため、故障時は海外への返送やサポート対応が必要になることが多く、時間も手間もかかります。
さらに、対応するのは外資系の配送会社やサポート窓口なので、やり取りに不安を感じる人もいるかもしれません。
だからこそ、最初から壊れにくいタフな機種を選ぶことや、
ユーザー自身で簡単にパーツ交換ができる設計のカメラを選ぶことは、見落とされがちですが実はとても重要です。
POV用途で使うと案外重くて不快
アクションカメラといえば「小型・軽量」のイメージがありますが、クラシックなデザインのモデルをPOV用途で使うと、意外と重さが気になります。
たとえば、GoProやInsta360 Ace Proシリーズなどは胸や帽子、バックパックのストラップに取り付けたとき、本体の重みで角度がズレたり、長時間つけていると肩こりや違和感を感じることもあります。
特にアクティブな動きが多い撮影や、長時間のVlog撮影では、「なんか疲れる」「気になって集中できない」といった小さなストレスが積み重なりがちです。
POV撮影をメインで考えているなら、できるだけ軽量なモデル(Insta360 GO 3Sなど)や、マウントの位置・安定性も含めて検討することが大切です。
デザイン変更のリスクあり
アクションカメラは1年ではそこまで大きく変わらないのですが、2年くらいのスパンだと性能が変わってきます。
ところが、買い替えるとしても前作のデザインからの継続性が約束されているわけではありません。
「アクセサリーをたくさん買ったけど新しいバージョンでデザイン変更があり、使えなくなった。」ということはよくあるのです。
リフレーミングが面倒
360度カメラの魅力のひとつは、**撮影後に自由なアングルでフレーミングできる「リフレーミング機能」**です。
「撮ってから構図を決める」ことで撮影の自由度が大きく広がりますし、シャッターチャンスを逃しにくいというメリットもあります。
ただし、それと引き換えに手間や負荷も大きくなるのが現実です。
まず、360度映像はデータ容量が非常に大きくなりやすく、保存スペースを圧迫します。
加えて、ファイルが重いため編集時の処理も重くなり、作業にかかる時間も長くなるのが難点です。
僕自身、リフレーミングの柔軟性が気に入っていて、おすすめしたい場面もあります。
ただ同時に、「全部を360度で撮る」というのはかえって非効率だと感じることも多いです。
目的やシーンに応じて、通常のアクションカメラと使い分けるのが、結局いちばんラクで賢いやり方だと思います。
画質が悪い
昔の機種では屋外の直射日光など、特定の条件下でしかいい感じの映像が撮れないこともよくありました。
画質がデジタル感強めで他のカメラで撮ったものと馴染まないことも多かったです。
今はどの機種も合格点レベルは超えています。
動作環境が限られる
アクションカメラの中には、暑さや寒さに弱く、気温の影響でシャットダウンしてしまう機種があります。
特に最近のモデルは高画質・高性能化が進んでおり、本体の発熱も大きくなっているため、夏場の撮影ではオーバーヒートしやすい傾向があります。
また、寒冷地ではバッテリーが急激に減ったり、そもそも起動しないケースもあります。
せっかく撮ったはずの映像が保存されていなかったり、いざという瞬間にカメラが止まっていたなんてことがあると、本当にショックです。
そのため、動作温度の安定性や冷却設計に関するレビュー・実体験談は、スペック以上に重要なチェックポイントです。
購入前には「どんな環境で撮るのか?」を想定しながら、動作温度への耐性も忘れずに確認しましょう。
4. 自分のスタイルで決めよう他人は他人
今あなたが使っているのがスマホでも、ミラーレスカメラでも、まずは「今ある機材で撮ってみる」ことがスタート地点です。
新しいカメラを買うのは
と確信できた時だけで大丈夫。他の機材で代用できるなら、それで十分。無理に買う必要はありません。
そうすれば、カメラ選びで後悔することはありません。
「このカメラを買えば自分も変われそう」
そんなふうに思ってしまうこと、ありますよね。
でもそれは、多くの場合幻想です。
が見えていないと、いくらスペックの高いカメラを買っても、“合ってない選択”になりがちです。
「自分のスタイル」×「それに合った機材」この組み合わせは自分で見極めていきましょう。
まとめ
「便利そう」「カッコいい」だけでは、カメラは使いこなせません。
買うときは「これさえあれば自分の撮影が変わる」と思っていても、実際はワークフローにうまくはまらないものもあります。
僕自身、使ってみたら自分には合わなくて売ったこともあります。
自分のスキル、目的、頻度、撮影スタイルに合っていないと、どんな機能も宝の持ち腐れ。
人によって「神機材」にも「ゴミ機材」にもなります。
自分にとっての「神カメラ」を選ぶには、冷静な自己理解が必要です。
そしてもうひとつ大事なのが、実体験。実際カメラに数十万、数百万出している人は必ずどこかで失敗も経験しています。
もし自分に経験がないなら自分の判断だけで何万もだして失敗する前に、課金している人を参考にしてリスクを回避しましょう。
ここまで読んで、「自分は失敗したくない…」と思ったら
アクションカメラを選ぶときにチェックすべきポイントがいくつかあります。
僕自身、失敗を重ねて気づいた「選び方のコツ」はつづきの記事でわかりやすくまとめています。